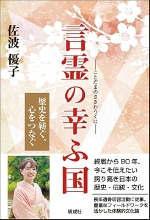
著者の佐波さんも、戦後派に属するから、左翼思想に染まった教育を受け、日本は加害者、戦前の日本は悪い国のように漠然と考えていた。
ふっと正気にかえるのが遺骨収集団に加わり、英霊たちのつどう靖国神社に参拝し、さらには皇居清掃奉仕にでかけてからだった。あまつさえ予備自衛官に志願して、国家防衛の女性防人となった。
そして和歌と古典に親しみ、多くの文献を渉猟しているうちに或ることに気がついたという。
『万葉集の時代から大東亜戦争まで貫かれている精神』である。
「万葉の時代から先の大戦まで千年の歴史を超える中で日本人としての同じ大和心が紡がれてきました。これは世界史の中でも他に例のないことだと思います。その心は、大御心を仰いで大義を果たそうとする使命感と、家族を思う暖かさ、優しさが同時に両立していることです。国のためならばという潔い強さと、残していく家族への深い愛情、自分の身を惜しまなくとも、残された家族の行く末を心配する優しさが矛盾ではなく同時に両立しているのです」。
紡ぎ、繋いだのは大和言葉である。
渡部昇一は大和言葉の例に「我々は自然界の道具として日本語を学ぶのではなく、桜花の美が分かる前に、日本語の中にまず桜花の美をみる」と言った。
宣長が詠んだ「朝日に匂う山桜花」である。
評者(宮崎)も次のように書いたことを佐波さんが引用している。
「漢語が頻出する、たとえば
日本は言霊の国であることをやさしい文章から強く思い出せて呉れた。猛暑に詠む清流のように。
|