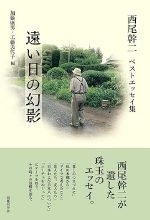
『西尾幹二ベストエッセイ集』と銘打たれた本書は西尾氏と親しかった加藤康男、工藤美代子夫妻の編集である。
残された珠玉の随筆には「ドイツで考えたこと」、「日本及日本人について」「ニーチェをめぐって」などがぎっしり詰まっていて一行一行に西尾さんの憂い満ちた深い思いが籠められている。
三島事件直後から、西尾氏は五年間ほど文壇から離れ、ニーチェ研究に没頭した。
その「遠い幻影」とは次の箇所に現れている。
「あの頃ようやく現実に合わない(左翼思想の)抜け殻と見え始めてきたのである。ハイジャック赤軍派事件や三島の死がしめす行動の過激化は、すでにして右の対立(左翼vs保守)が消滅しかけていることを証拠立てている。(中略)70年代に入って対決の時代はまるで嘘のようにぱたっと終わった。代わりに無気力と無関心をトレードマークとする『しらけの世代』が登場し、井上ひさしが人気を博し、言葉の遊びと江戸戯作調がモードとなる。イザヤ・ベンダアン『日本人とユダヤ人』(1970年)以来比較文化論が流行し、日本文化は三島的決断の美学から、山本七平的認識の相対化論に所を譲った。文壇は以前にもまして自閉した専門家集団と化し、文芸論争いは起こらなくなった」
なるほど軽薄が売りの井上某や「言葉の遊び」はたぶん江藤某、「江戸戯作」とは野坂某のことだろう。
文壇は三島以後、これという作品はない。日本の伝統を表現し古典として残るような作品もなければ、魂が揺さぶられるほどの作家の出現はない。
小説家より漫画家が全盛となるのも宜なるかな。論壇にいたっては昂奮する、瞠目するべき論客が不在となって、おそらく西尾さんが最後ではないのか。
ゆえに「私の居場所はなかった(中略)。私の対決の相手は幻影の如く消え、敵のない私の対決ポーズはもはや完全に滑稽でしかない」(22p)
そして西尾氏が沈黙してきた三島を語り出すのは事件から四半世紀のちのことだった。歳月は決して三島由紀夫を風化させなかった。三島は「死後も成長し続けた」(秋山駿)のだ。
また萩原朔太郎に関しての記述が面白い。西尾氏が文学青年時代、萩原に熱中し、全集もそろえたほどだった。
「しかしどういうわけかだんだん嫌いになった」
というのだ(79p~80p)
「その叙情詩の多くは、いまでも私の感情の深部を揺さぶるものを持っているが、彼の書いた論文やアフォリズムの類は今ではほとんど読むに耐えない。私が朔太郎を愛読するようになり、しだいにそれがつまらなくなってくるプロセスが私の青春から成人への歩みであったかもしれない、と思っている。(中略)朔太郎の深刻がかった理屈っぽさと、文学少年の真情の奥底に訴える憂愁の詩的リズムとの交配に魅きつけられたのかも知れない」
そしてこうも言われる。
「私が求めているものはかつても、今も、少しも複雑なものではないのである。単純に美しいものが欲しいというだけのことだという気がしている。複雑に手の込んだ、人工的な文学に対する嫌悪がいつも私を苛立たせるのである」(81p)。
「人工的な文学」とはまさしく大江健三郎であり村上春樹のことだろう。
意外なエピソードも挿入されている。
テレビの討論番組で知り合った才女は高市早苗と言った。新しい歴史教科書をつくる会の熱心な支援者だったこともあり、彼女の結婚式に呼ばれた西尾さんは、そのときの雰囲気を、まさに日本の政界の風景を映画のフィルムのように伝える(詳しくは本書で)。
本書を編んだ加藤康男氏が指摘する。
「若き日の西尾さんの切っ先鋭いテキストから今なお進行中の諸問題にいたる全文業が(本書に)に収められた。この全集を座右に置けば、いま日本国民が何をなすべきか、逼迫した問いかけが胸を衝くに違いない」。
西尾さんは小泉純一郎を「狂人宰相」と酷評し、安倍晋三をほとんど認めなかった。まさに評者(宮崎)が『正論』の西尾追悼特集号に書いたように「西尾さんの白刃は収まる鞘がない」のである。
|