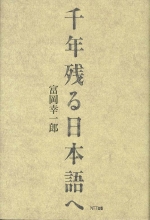
文芸評論の分野では単行本の上梓そのものが珍しい。しかもこの書籍、なんとも題名が良い。
千年、残るほどの強き、そしてやさしき日本語。雅(みやび)とたおやかさと優雅さと、みずみずしさ。源氏物語も、万葉集も、日本が世界に誇る古典である。
鎌倉文学館館長でもある冨岡幸一郎氏は、なぜこの本を書いたのだろう?
どうやら三島由紀夫の言葉が原点にあり、バネのような動機となったように考えられる。
というのも、富岡氏はこんな風に書き出すからである。
「三島由紀夫は、村上春樹が『風の歌を聴け』で、作中の時間として設定した1970年に自決したが、その直前、『日本文学小史』という日本の古典文学を論じたエッセイを遺している。古事記、万葉集からはじまり江戸期の近世文学(近松、西鶴、芭蕉、馬琴)までの日本語の歴史を、独自の視点から論じようと試みた文学史であった。残念ながらその死によって源氏物語を少しばかり論じたところで未完に終わった。(原文改行)しかし、古今和歌集にふれた個所で、作家は、ここで『日本語というものの完熟』を成就したという。古今和歌集の日本語こそは『本当の意味の古典美』を示している。それは日本人の『文化』の『白昼』(まひる)である、と」(冨岡同書、11p)
文化の「白昼」(まひる)を経験した民族は、そのあとは「夕焼け」
三島由紀夫の言はこうである。
「(万葉集は)古代の巨大な不安の表現」。
「文化の白昼を一度経験した民族は、その後何百年、いや千年にもわたって、自分の創りつつある文化は夕焼けにすぎなかったのではないかという疑念に悩まされる。明治維新ののち、日本文学史はこの永い疑念から自らを解放するために、朝も真昼も夕方もない、或る無時間の世界へ漂い出た。この無時間の抽象世界こそ、ヨーロッパ文学の誤解に充ちた移入によって作り出されたものである。かくて明治以降の近代文学史は、一度としてその『総体としての爛熟』に達しないまま、一つとして様式らしい様式を生まぬまま、貧寒な書生流儀の卵の殻を引きずって歩く羽目になった」(『日本文学小史』講談社、1972年11月)。
夕映えの赫々たる陽光、三島の存在も千年残る文学である。それゆえに多くが「日本文学小史」全編の完結を期待したのだった。
さて千年残る日本語を模索する作家が現代日本に居るのか、いないのか。
冨岡氏は本書で古井由吉、朝吹真理子、リービ英雄、藤沢周、辻原登らを取り上げて評価する一方で、村上春樹や田中慎弥、柳美里、楊逸、温又柔らを論じる。
在日外国人が四人もいるのは、自然にみについた言葉を操れる日本人作家と違い、ひとつひとつの意味を、体感的に覚えながら、母国語と日本語との距離と壮絶に戦いながら、日常の行為、風景を日本語を用いての、ふさわしき表現を試行錯誤で追求し身につけた経過をもっているからである。
とくにジャパノロジストとして日本文学の翻訳に従事してきたリービ英雄が、ある日、山上憶良が渡来人であったことを知って小説を書く決意をした。
リービの中国旅行記などを読むと、この人はアジア主義者かと思うほどである。
評者(宮崎)は個人的にリービ英雄と辻原登を評価しているので、この二人を如何に冨岡氏が論じているかに興味があった。
異色作家、リービ英雄の登場
リービ英雄を論ずるにあたって、富岡氏はいきなり保田與重郎との比較から入る。
「昭和13年5月2日、日本浪漫派の代表的論客である保田與重郎は、詩人の佐藤春夫とともに朝鮮半島、満州(現在の中国東北部)、北京から蒙古(現在の中国内モンゴル自治区およびモンゴル国)方面へかけて四十余日の大旅行へと発った。(中略)保田は帰国後の十二月にこの一連の記録を『蒙彊』という一冊の本としてまとめた。(原文改行)北京の街に失望した保田は蒙彊地方の雄大なその自然に面して、深い感動をおぼえた。二十九歳の保田は大黄河に一人たたずみながら、脱亜入欧の明治の近代化、西洋化以来の日本人が、この遙かなる大陸において、大きな精神の転換をなすべきだとの確信を得た」(同63p)。
保田は実際には次のように書いた。
「我が国はまず、世界に先んじて十九世紀の一切のイデオロギーから訣別する。問題は、十九世紀の完成をなさなかった日本の文化が、アジアによってより大きい転向をなしつつあるということである。(中略)日本の転向の萌芽を象徴するものは『蒙彊』である」。
冨岡氏はリービ英雄の『天安門』が、つまり「大陸中国を、この島国の言葉で描くこと。保田の『蒙彊』から半世紀を経て、それは現代の日本語作家として登場したアメリカ人のリービ英雄によって試みられた」というのである。
辻原登の言葉の豊かさ
辻原登について冨岡氏は次の指摘からはいる。
「辻原は『表現者』(08年五月号)の座談会『物語の源泉へ』のなかで、中国には『物語』という漢語はないといい、中国語では通常これを『グーシー(故事)』のことであると指摘している」と。
辻原は、こう言っている。
「物語と呼んでいるのは日本でつくられた漢字です。これはしかも翻訳語ではない。それはなぜかというと僕は勝手にこう思っているんですが、日本語の大和言葉における『もの』というのは目に見えないものなんです。ヤマトの人たちが『もの』と呼んだときは、本来は自信の中にいるべき何かが、なんらかの事情で体の外へでたもの、それをどうやら『もの』と呼んでいる」
冨岡氏はこの発言を受けて、次のように続ける
「情報革命と言われる世界的現象のなかで、空間が無限に拡張され、言葉が断片化し、ゆっくりとして時間の流れが失われていくなかで、あらためて言葉が孕む『もの』の力を、小説という表現ジャンルによって(辻原が)表そうとしてきたのではないのか。それは近代文学の過去のパターンに戻ることではなく、日本語の大和言葉における、まさに『もの』を現代語のなかで、よみがえらせることではないか」
そして冨岡氏は辻原登の「ダッタンの馬」を高く評価して次のように言う。
「この作品の真の醍醐味は、まさに異国の発語の谷間を乗り越え、異なる文字の形を飛び越えてゆく、そのコミュニケーションの奔流を、現代日本語によって表記し、描いているところにある」(162p)。
この辻原の小説は『日本経済新聞』に二年ほど連載されていたので、毎朝、愉しみに愛読していた。
久しく日本文学が忘れてきた浪漫的冒険の、その熱血がほとばしるような作品だった。ところが日本の文壇は左翼や無国籍リベラル作家にほぼ支配されているため、このように根源的文学、浪漫的熱情の冒険譚は無視されるか、敬遠される。だから文壇でもマスコミでも大きな話題にならず、本屋でも目立たないという文化の退嬰が起きているのも事実である。
朝吹真理子の登場は「芥川賞の歴史における時代的事件」か?
紙幅も尽きたので、ほか作家たちに触れる余裕はないが、富岡氏が朝吹真理子の出現を芥川賞の歴史における『時代的事件』という比喩を用いて、たいそう高く評価し、今後の期待していることに驚かされた。
『古語辞典』が大好きという彼女の文体を冨岡氏は「古語がよみがえる時間」であると言い、「村上龍、村上春樹の両ムラカミの登場の衝撃とは明らかに違う、朝吹真理子という才能の出現は、おそらくこの現代という時代の表層(彼女のいう「匿名の人たちの唇や吐息」の触媒)に深く関わっているのではないか。(原文改行)失われた古語が、まさに現代の『言葉として新たな生』を回復しはじめる」(36p)。
久方ぶりに本格的な日本文学の篤い評論を読んで、時間があっという間に過ぎた。
|