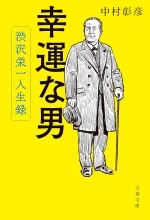
渋沢栄一は新一万円札の顔、徳川慶喜に見出され、最後は慶喜を保護し、日本に資本主義の仕組みを根付かせた偉人である。
日銀券一万円札の顔としては聖徳太子、福沢諭吉に続く。
幸田露伴が伝記を書いたのを嚆矢に多くの渋沢栄一評伝が出た。財政の論議では大久保利通と対決し、西郷隆盛を説得し、伊藤博文、井上馨、大隈重信らと丁々発止。この人物は「日本資本主義の父」とまでいわれるが、すべてが幸運に支えられた人生行路をたどり九十一歳まで生きて天寿を全うした。
若き日に栄一はテロを決行しようとした。その後、パリ万博で幕府が倒れたことを知り、慌てて帰国するが、学ぶべきを学んでいた。帰国後、明治政府の財政状況を安定に導き、五百もの企業を育てた。
「英雄色を好む」のは古今東西同じだが、妾腹の子供たちにも援助を惜しまなかった。
本書は三年前にでた『貪らなかった男』(文藝春秋)の文庫化であるが、百枚を書き足しているので新編である。
その加筆部分が第二十話、二十七、二十八、三十四、そして第四十話だから、この部分は新たに読んだ。
理財家としての伝説は戊辰戦争の戦費調達に遡る。
渋沢のアイディアは金札の発行だった。ところが不換紙幣なので信用が薄く、事実上の交換比率、つまり利息は20%から50%だった。インフレ必定である。
そこで渋沢が打った手が換物投機つまり米穀、肥料から糠、干し物の買い付けである。当然インフレが襲うから利益が出る。それを軍事金に充当させる。今日でいうファンド筋の新金融商品の独創性に匹敵する。
理財の才能を見出された渋沢は最初の渡仏で、2000両の旅費、預かり金を四倍の八千両とし、くわえてスナイドル銃360挺を土産とした。
この理財ぶりに周囲は目を丸くした。
明治維新は政局と武闘、はかりごとと軍備が華々しく論じられ、西郷、大久保、竜馬、晋作、木戸孝允、新撰組が大いに論じられて映画、テレビ、大活躍のチャンバラも入るが、実際に維新を設計したのは大久保と木戸孝允である。黒幕が岩倉具視、また精神を唱えて幕末に散華した吉田松陰、多くの志士が学問を乞いに駆けつけた藤田東湖などが高く評価される。
しかし実際に国家経営にあたってその主柱となる財政を支えたのは誰か?
「廃藩置県をおこなった当時、日本という国の国家予算はなきに等しかった」
にも拘わらず大久保は陸軍に八百万円、海軍に二百五十万円を要求し、財源をどうするかは慮外だった。結局、「当時の日本の軍事は歳出全体の29・82%にまで膨れあがった」。
富豪からの取り立て、外国からの借金にくわえて金銀貨幣の改鋳(改悪)を急ぎ、その一方で、
「栄一は廃藩置県の際に、諸藩の所有する藩札や藩札を明治政府発行の公債と貨幣に引き換えるという面倒な役をよくはたした」(205p)
西南戦争はただでさえ紙幣を、担保するもの、裏付けなしの発行でインフレが昂進していた時代だったから歳出歳入のバランスは崩れた 西郷軍は西郷札を発行したが、明治新政府も同様の手口で紙幣を印刷し続けた。
明治十年師走までに「新紙幣を二千七百万円発行、第十五銀行から借りあげて軍事費とした紙幣だけでも一五〇〇万余円(中略)。西南戦争征討に用いられた軍事費総額は四一五六万円だから、そのうち半分以上は新規発行紙幣だった」(245p)。
無謀な資金調達だったのだ。
渋沢栄一は銀行経営を実践し、割引手形、荷為替などを考案し、やがて銀行経営を起動に乗せた。
これまでの維新史とは別の角度から改革の経済的本質に迫った力作となった。
|