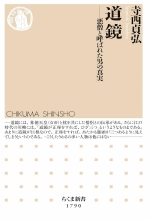
道鏡ほど偏見の風圧によって悪魔風に誤解され、それも一方的に極悪人とされてきた歴史的人物は稀有である。もうひとりを挙げるとすれば明智光秀だろうが。。。。
称徳天皇と同衾していたとか、イチモツが巨根だったとか、天皇の位に就こうと野望に燃えていたとかは、すべて嘘、それも数百年後のフェイクである。
かれは入唐経験こそないけれども、サンスクリットを読みこなせた。学識豊かな高僧だった。
称徳天皇が、一度は譲位した淳仁天皇の廃帝を画策し、宇佐神宮の神託の偽造を裏で画策し、仏教界の「法王」、同時に太政大臣として抜擢した道鏡とともに、天皇と法王の共同統治という、未曾有の政体の変革、皇国史観的にいえば「国体の破壊」を構想した。
その政治思想のいかがわしさを『続日本紀』は道鏡の所為にしたのではないか。
この詳細な経過を評者(宮崎)も拙著『二度天皇になった女性』(ワック)で精密に考察した。
拙論は孝謙天皇が淡路廃帝ののち、称徳天皇として重祚されるまでの過程を基軸として、藤原仲麻呂、吉備真備、藤原百川を副主人公として、安倍内親王時代の聖武天皇の爆発的な仏教の影響から、家庭教師だった留学帰りの吉備真備への信頼、そして治療を成功させた禅師・道鏡の登場を伏線に捉え、国体の危機を論じた。
保良宮は滋賀県石山に位置し、藤原仲麻呂の近江国衙に近い場所だったが、道鏡は、この保良宮へ赴き、なぞとされる「宿曜秘法」(すくようひほう)を用いて、称徳天皇(当時は孝謙上皇)の治療にあたった。上皇は快癒され、道鏡への寵愛が始まった。
寺西博士は、この出会いを『宿曜占文抄所引道鏡伝』という古文書にあたり、天平宝治六年(西暦762年)四月のこととする。
本書は評者と同様な解釈を縷々展開されているが、さすがに歴史学者としての強みを活かして、適切な文献資料を探しだし、隅々にまで目を光らせて、文章の作為や齟齬を発見しつつ、主に位階の変化を時系列に追って歴史推理を組み立てている。
とくに正倉院の図書貸出しは師の良弁の使いとして道鏡が署名した貴重な記録だが、多くの仏教教典のなかで、道鏡が興味を惹いたのが呪術に関しての経文だった。おそらく之により道鏡は宿曜秘法をマスターしたのだ。
寺西は続ける。
「道鏡の仏教とは洗練された新来の仏教ではなく、我が国固有の呪術信仰と仏教が融合した呪術仏教だった。(中略)社会の基層に存在しており、空海が真言密教を携えて帰朝すると、その教義は平安初期の日本社会にすぐさま歓迎されて、大々的に流行した」(74p)とする指摘に注目した。
正倉院の記録から道鏡の青年時代の謎を解明し、また道鏡の兄弟たち栄達ぶりを、その位階、その異様な昇進の経過を時系列化し、全体像として称徳天皇と弓削道鏡の出会いから別れまでを活写する。
本書で「えっ」という指摘は、称徳天皇が最後の病床で連絡役をしていた女官は吉備真備の娘ではなく妹だったこと。義淵と道鏡は師弟関係であり、直接の師は良弁。少年時代の道鏡は義淵の供侍童子(ともざむらいどうじ)として奉仕していたこと。
また弓削は物部一族とされるが、その弓削一族のなかでも、道鏡は傍流でしかなかったこと。『続日本紀』の道鏡禅師大臣の任命に関する箇所には藤原仲麻呂を批判する傍らで、さも弓削一族が名流のような書き方をしているが、『先祖の大臣』というのは蘇我氏に滅ばされた物部大連弓削守屋を意味し、大連は『大臣』ではないから矛盾するとする。
また東大寺に対抗した西大寺の建立に道鏡はほとんどからんでいなかったと著者は推定しているのも通説とはことなり意外だった。
評者は文献の照合作業より、関連するあらゆる現場に足を運んで、その土地に匂いを嗅ぎながら、その土地に伝わる稗史と正史の齟齬を発見するドキュメント的な作風を重視しているので、本書のような文献重視の営為には教わるところが多いのである。
淳仁の廃帝は、道鏡ではなく称徳天皇が積極的だったこと、禅師への昇格は道鏡の故郷弓削寺で行われ、仮御所としたばかりか、のちに西京としたほど熱意を込めた。
評者は左遷先で道鏡が住民から慕われ、また茨城県石岡のはずれ、竹原にも孝謙天応の祠と道鏡塚があることの経緯を知りたいと思ったのだが、大納言にまで出世した弟・弓削浄人一族のその後のことは書かれていても、道鏡左遷以後から死までの考察がないのは残念である。
|