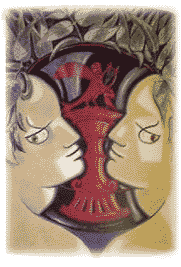|
三島由紀夫文学紀行 その3 パリ |
| 花の都・パリでの三島は陰鬱なる冬をおくった |
|
陰鬱な空、あの底冷え 三島は初の海外旅行では南米がすっかり気に入って、リオのカーニバルを見るために滞在を少し延ばし、それからレイモン・ラディゲを産んだ、いや三島の二十代までの作品群に巨大な影響を与えたフランス文学の、花の都へとやってくる。三島が27才のときである。ところが三島のパリの印象は甚だよくない。「冬のヨーロッパを旅しているあいだ、私はいつも太陽にあこがれていた。パリやハンブルグで、昼のあいだずっと灯りつづけているネオンサインにおどろいた。朝起きるときから外光は夕方の薄明で、ネオンの色は少しも薄れず、夜よりもむしろ鮮やかに見えるのである。パリの冬の来る日も来る日も頭上を閉ざしている陰鬱な空、あの底冷え、永遠の鼠いろ、…そしてそこかしこにきらめいている寒色のネオンサイン、あれは私にはとてもたまらない。私にはどうして人間があんな陰鬱な冬を生き続けることができるのかふしぎでならない。いまさらながら、日本は何と太陽の恵みによくしている國であろうと思う」(「外遊日記」)。 | ||||
 パリの伝統と前衛を象徴するガラスのピラミッド | ||||
|
パリはいつも黄昏というイメージを三島が終生抱いていたとは思えないけれど、ニューヨークほど頻繁に通ったわけでもなく、仏蘭西語がしゃべれるわけでもなく、まして初回の旅行ではパリで不愉快な事件に遭遇した(ドイツ語なら、少しできるんだがな、と三島はパリ生活中、通訳兼ガイド役でもあった黛敏郎に言ったそうだ)。パリの下町で闇両替に引っかかって有り金すべてに近い、2000ドルのトラベラーズチェックを盗まれたのである。再発行されるまで三島は身動き出来ないことになったのだ。大事なアテネとローマの旅程が短縮される原因である。一ヶ月もパリの安ホテル「ぼたんや」に宿泊を余儀なくされたのも路銀を盗まれたからで、これが三島をパリ嫌いにして所以といわれるのだが、真相は分からない。対照的にパリを目一杯楽しんで、青春そのものを送ったのがヘミングウエイである。彼のパリの印象とはーー 「もし若いときにパリに住む幸運に巡り会えば、後の人生をどこで過ごそうとも、パリは君とともにある。なぜならパリは移動する祝祭だから」(「移動祝祭日」、今村盾夫訳)。三島はパリになじまなかった。それでいて世界の中で三島文学の精神性に最初の理解を示したのは圧倒的にフランス人であったのだが。「パリ憂国忌」も、竹本忠雄によれば事件後、直ぐに仏蘭西の知識人が集まって開かれたという。だがパリと三島由紀夫は景色を通しては連結しない。三島はパリの景色にあまり興味がない。彼の興味はあくまでも仏蘭西の詩人、芸術家らの内面なのである。 若き日の三島がレイモン・ラディゲの虜になったことはよく知られるが、16才で詩の天才として登場し、20才でチフスにかかっての夭折という悲劇性がことさら三島の関心を寄せ付けた。加えて「恐るべき子供たち」を書いたジャン・コクトーが巨大な影を三島に投げるのである。三島は自己に巨大な影響を与えた、たとえば保田与重郎や、ダヌンツィオについての記述が意外に少ない事実を今日ようやく多くの評論家が指摘するようになっている。同様に三島はレイモン・ラディゲについては饒舌に語ったが、コクトーについては多少書いてはいるものの、饒舌ではない。若き日の三島は、自己韜晦的であったからだ。
ラディゲと三島の「盗賊」 先に話題がかなり脱線した。パリでのことはレイモン・ラディゲをまだすこしく綴らなければならないだろう。「肉体の悪魔」と「ドルジェル伯の舞踏会」の二冊だけで、しかし不朽の名作をのこして二十才でこの世を去ったのだから「滅びの美学」に憧れ、日本浪漫派に酔いしれていた三島にとって「ラディゲ病」に罹り、その青春像へと直接的に結びつくのは極々自然の流れである。まして三島は少年時代、20才で死ぬことにも密かに憧れていたのだから。 しかしラディゲの作品は「典型的な古典主義の手法で書かれたラファイエット夫人やラクロの小説を模倣したものであり、その当時の手法とは全くかけ離れたものであった。(中略)三島がいかにラディゲから影響を受けたかは、ラディゲについて書いている数多くの作品をみても明らかだ」(ベアタ・クビャック・ホチ「ラディゲの役割」国見晃子訳、「世界の中の三島由紀夫」勉誠出版所載) 三島は十代の後半に「ドルジェル泊の舞踏会」を堀口大学訳で読み、その文体の華麗さにも感動した。「私は、堀口氏の創った日本語の芸術作品としての「ドルジェル泊の舞踏会」に、完全にイカれていたのであるから。それはまさに少年時代の私の聖書であった。」(全集三一巻)。三島作品でラディゲの影響が最も強く出ているのは「純白の夜」と「美徳のよろめき」である。ラディゲは「クレーブの奥方」やラクロに影響を受け、しかもコクトーの推挽で文壇にでた。二人はその前後から同性愛の関係にあった、といわれる。(念のため今年5月20日まで渋谷東急bunkamuraで開催されているコクトー展を見学されるとよい)。
コクトーへの傾斜 三島がコクトーへの興味を「映画」への関心に焦点を当てて書いたのが「ジャン・コクトーと映画」(「文芸」昭和28年6月)である。コクトーは既に「美女と野獣」とか「恐るべき親たち」「双頭の鷲」などの名作をいくつかものにしていた。三島はじつに映画好きで筆者が知っている頃は高倉健、鶴田浩二ばかりだったが、昔は洋画をよく見た。海外でも行った先で夜、暇になると映画を見たことが往々にしてあると「外遊日記」にはでてくる。 | ||||
 モンパルナスのカフェ・ドーム | ||||
|
コクトー、70才のときである。 三島のパリ 冒頭でも述べたように三島はパリの情景にまるで興味を持たないかのように作品の舞台にさえ選んでないのである。仏蘭西文学へのあこがれは人間の内部への省察、洞察であっても景色としての美的興味の対象にはなりにくかったのかも知れない。また天の邪鬼としての三島の性格も考慮に入れなければならないだろう。なにしろ三島が登場した日本の文壇はといえば小林秀雄、大岡昇平、中村光夫、村松剛、遠藤周作、その他大勢、悉くが仏蘭西文学専攻ではないか。東大法科出身の三島としては仏蘭西語を操れない林房雄、川端康成に近親感を覚えたのも自然の帰結であると思える。その三島が仏蘭西通の黛敏郎、村松剛とのちに親交を深めるのも二律背反的ではあるが。 | ||||
 パリ16区は閑静な高級住宅街 | ||||
|
三島が逗留する羽目に陥ったパリは、重苦しく寒い三月。そういえば三島はブラジルを廻って陽気な太陽に打たれご機嫌のまま、文学で憧れてきたパリについてろくな目に会えなかったのだから実際のパリを、その後の人生で毛嫌いすることになる。二回目も三回目のパリも素通りか短期滞在で、それに比べて何回でも行きたいところはローマだった。 |
2000-2008 MIYAZAKI MASAHIRO All Rights Reserved